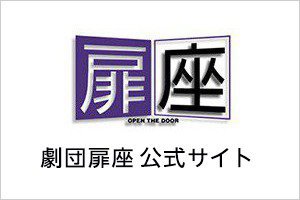辻井伸行クンのこと
今夜はちょっと百鬼丸を離れて……
ピアニスト・辻井伸行クンのことを。
辻井クンと、最初にお会いしたのは、彼がショパンコンクールに向かうという時だった。
仲間内の壮行会みたいなのがあり、たまたま縁があって、そこに参加した。
ほんの10人ぐらいの、内輪の会だった。
私の友人が、彼の本のライターをやっていて、たまたま芝居の帰りに雑談していて、こんな天才少年がいるんだが、
と話を聞き、即座に会ってみたいと思って、特別に参加させて貰うことになった。
その時、レストランの個室で、たった10人のためだけに、彼は数曲弾いてくれた。
正直、私はクラシックピアノのことは分からない。
ただ盲目の彼が、手元を見ることなく魔法のように、多彩な音をはじき出す、ことに驚愕し、
その音色の美しさを聴いて、上手いと思うのは当たり前のことながら、じゃあ、どれほど上手いのか、聞き比べるほどの教養も経験もないし、ジャッジの基準が私の中にない。
ただ
弾きながら、全身を激しく揺する、その演奏スタイルに目を奪われ、たちまち引き込まれた。
ショパンじゃなくて、モダンジャズか何か弾いてるみたいだなと、思った。
伸行クンは、ノッてくると、カラダが自然に動き出す。
彼をずっと見てきた人たちは、そう言っていた。
そして私が、その日、何より感動したのは、クラシックの後にオマケで弾いてくれた、彼のオリジナル曲だった。
デビューCDにも収録されている、
『ロックフェラーの天使の羽』とか。
初めてニューヨークに行った時、ロックフェラーセンターにある天使の彫像に触れた、その時の思いを即興的に弾いたものだということだった。
すぐにも、これを芝居に使いたいなあ、と思った。
繊細で美しい、アダージョである。
不思議なことだけど、
盲目の彼の作った曲から、その映像が見えてくるのだ。
まあ
クラシックの門外漢としては、素人のためにも、こんなに優しいメロディーを奏でてくれる、その優しさも心にしみたのだと思う。
偏屈な人も多いからね。
クラシック界には、
でも辻井クンは、自由だなと思った。
そもそも世界最高の激戦であるショパンコンクールだって、皆が早すぎると止めるのに、ショパンが好きで好きでたまらないから、ただその思いだけで、チャレンジを実現させたのである。
他のコンクールは、そこまで出たいとは思ってないけど、ショパンコンクールだけは、どうしても出たいんですと、16歳の彼は熱く語っていた。
その模様は全世界にネット配信されていて、私も、日々チェックして、応援をしていたものだ。
ファイナリストにはなれなかったが、準決勝まで勝ち上がり、批評家賞という特別賞を獲得していた。
そもそも受験者の中でも、最年少だったので、それだけで驚愕すべき快挙であった。
その一方でカラオケでは、氷川きよしを歌い、ピアニストなら普通は敬遠すべき、スキーだとか、キャンプなど、やりたいことはとくにかく全部やるというのが、彼と、彼の家族の方針で、そういう世界の広さが、とても好ましく思えた。
しかも、盲目なのだからね。
スキーの危険さだって、半端じゃないのに。
そのころは
ちょうどミュージカルを作りたいなあ、と思っていた頃だ。
冗談半分で、君、作曲してくれない?と振ってみたら
やってみたいと言ってくれた。
実際、彼なら、鼻歌を並べただけで、たちまち出来上がりそうな気がした。
実は、昨年の厚木市民劇『リバーソング』の時に、一曲、みんなで合唱の出来るような、川の唄を作ってもらおうと、オーダーを出していた。
辻井クンの伴奏に合わせて、大勢で歌えたら、サイコーだなと思って。
鼻歌でいいから、一曲ちょうだい、みたいな今考えたら、おそれを知らぬ注文の仕方であった。
辻井君は、一昨年、池袋の『ドリル魂』も観劇に来てくれていたのだ。
それで、舞台にも興味を持ってくれていた。
ただ、ザンネンながら、夏休みの前後のことでもあり、彼とのスケジュールが合わなかった。
すでに、業界では注目の人であったが、実現寸前までいっていたので、今考えたら、ちょっと無理しても、やっとけば良かったと、思う。
またチャンスがあるだろうと、軽く考えた、私が甘かった。
そして、迎えた今年の活躍である。
当分、そんな時間は取れないだろうな。今や時代の寵児にして、クラシック界の救世主だものな。
今日、また表彰されたとニュースに出ていた。
しかしそれもまあ、しごく当然のことである。
ただ
願わくば、彼の自由な感性がどうか、型にはめられて、ゆがめられたりすることのなきよう。
演奏家としてだけでなく、希代稀なる作曲家、創造者としても、自由の翼を広げて活動を続けてくれるよう、
願う。
そしてそして、ぜひいつか、再会の時がやってくることを期待する。