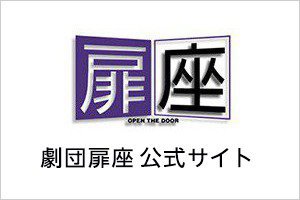きらら の記 その2
37年前の きらら浮世伝 の演出家、故・河合義隆監督が『青春グラフティ・坂本龍馬』の大成功で名を馳せ、第2弾として『青春グラフティ・福沢諭吉』が創られ、その際に諭吉を演じたのが先代の勘九郎さんだった。
ちなみに映画『Ronin』という作品があり、これが龍馬の映画版の位置づけとなっている。ただ、この大作映画は思ったほどには当たらず、そのことが監督の苦悩の一因であったと思われる。何しろ自分は天才だ、俺と拮抗するのは日本ではクロサワだけ、と公言してはばからぬ人であったから、少しばかりの成功では辻褄が合わないのである。
天才は大変だった。
その撮影時にも驚愕のエピソードが数々あるのだが、それはまた別の話だ。
河合ワールドのキーワードは青春であった。
きらら浮世伝 も青春グラフティのひとつとして製作された。
若く熱く、ぶつかりあい、疾走する若者たちの姿。貧しく名もない新鋭たちが為した芸術革命、反権力の闘争……
で、それは作品のみならず、作品作りの姿勢にも色濃く反映されていた。
きらら 初演の稽古はセゾングループが建てた新しい森下の稽古場だった。そして日暮れ前に稽古が終わると、毎日必ず、飲み屋に繰り出して飲み会が始まった。
しかし店に上がったのはごく初期で、ある時から一座は近所の魚屋さんの店先で、適当に刺身など頼み、酒屋や販売機で飲み物は調達して、ビール箱などに腰かけて飲み始めた。
そのオープンエアな大宴会は下町のこととはいえ、かなり目立った。
当時、すでに勘九郎さんは全国区で顔も知られていたし、キャストには美保純さんはじめ有名人も大勢いたから、たちまち人だかりが生まれる。そのうちに家のおかずを差し入れに来るオバサンが現れたり、通行人がいつの間にか混じっていたり横丁中を巻き込んで、連日、お祭り状態となった。
それは、ある意味、武士も町人もなく垣根を超えて、狂歌という洒落を愛する仲間たちと吉原の座敷でふざけ、馬鹿騒ぎをする、重三郎たちグールプの姿そのものであった。
ここでは歌舞伎役者もテレビ俳優もアングラも若手小劇場もアイドルも、混然となり、路上飲みをした。
青春のカオス。
私はといえば、一世一代の覚悟で臨んだ稽古の最中での突然の全力飲み会、その異様なテンションに付いて行けず、ただただ気圧されて、そんなにはしゃげなかった。表面上は楽しんだふりをしていたけれど、むしろ、冷静に先輩たち兄さんたちの激烈に傾く姿を観察するように眺めていた、と思う。
稽古だけでも大変なはずなのに、それ以上にエナジーを注いで祭りに興じる、その姿は私には自傷行為、破滅願望にさえ見えていた。
この人たち狂ってるよ……
きらら浮世伝 には、大きく分けて二世代のグループが登場する。
重三や歌麿、春町、南畝の中心世代。
そして重三の弟分として描く、山東京伝を間に挟んで、蔦屋の店員として働いた、曲亭馬琴、十返舎一九、版木彫りの職人だった葛飾北斎ら、ニューカマーの世代。
その中心メンバーのうち、幕臣でありつつ戯作に興じていた太田南畝だけは、時勢を読んで見事に身をかわし、戯作精神を抑えきって時代の荒波をやり過ごし無事でいたが、他のメンバーは皆、自由の制限、文化抑制の改革の嵐の中でも「自分らしさ」を捨てきれず、むしろ反骨精神で、らしさを発揮してしまったために、酷い目に遭っている。
美人画のあの繊細な絵の歌麿でさえ、臆することなく、破滅の炎の中に自ら身を投じて滅んでしまった熱い魂を感じずにいられない。
美人画を描いて、その魔法の手に鎖をはめられ、そこからの急死……
誰が見ても美しい絵を描く、あの絵師までも狂ってる。
そういう意味でも、あの時の河合監督たちの姿は、私の中で、きららの重三たちにリアルに重なる部分がある。
ヒリヒリしながら洒落に興じる。酒に酔い、暴れ、笑い、泣く……
(本当にあの人たちは、やたらに芝居を、人生を、恋を語って、泣いて怒鳴り合っていた、かと思うと突然笑いだし、しまいには抱き合っていた)
どこか壊れた人たち。
それに対してニューカマーは、皆、しぶとく生きた。馬琴も一九も北斎も、それぞれの仕事を粘り強く、きちんとやり遂げた。
これは私の私見だけど、
ニューカマーたちは、先行世代の人たちを畏怖しつつも、どこかで距離をおいて冷淡に眺めていたと思う。破滅の崖っぷちを好んで歩くような先輩たちの荒行をじっと観察していた。
そして何をすべきか、自分はどう生きるべきか、それぞれに深く考えた。
結果、俺は生きる、生きて貫く、と決めたんじゃないか。
ではその決定に、先行世代の狂気は、反面教師でしかなかったか。
それは断じて否である。
ニューカマーたちは、その奥底で強い憧れを抱いたはずだ。そこまで狂って、自分たちの世界に熱狂する人間たちの姿に。
なぜなら、芸術表現とは自らの力で一心に狂って見せることだから。
自らの力で生じるのではない狂気は、それは病か、クスリか神の所業である。
人の営みとしての表現は、目覚めのなかで生み出す狂気だ。
そしてそして、実は先行世代の人たちは、その狂乱の姿を、後ろを追いかけて来る次の世代の若者たちに、どこか意図的に見せていたんじゃないか。
よく見ておけ、と言わんばかりに。
お前らも、ここまで来たら認めてやる、と。
あの きらら の時の狂宴の日々を、私がこれほど鮮明に覚えているのは、その仕事が大きなチャレンジであったというだけではなく、表現者として生きる私の通過儀礼であったからだと今は確信している。
きらら はいろんなものを私にくれたが、中でも最も大事なことは、表現者としてその先を生きてゆく覚悟であった。
その通過儀礼の体験の中で、河合監督や勘九郎さんは、儀式の司祭であり、メンターだった。私は彼らに精神注入された。
お前も狂って見せろ、と。
俺に敵うのはクロサワだけだな。そんなことを言う、意外に童顔の監督。
あの頃は、リアルに、この人馬鹿じゃないか、と思ったものだ。天才なんて自分で名乗るものじゃないだろう。でも、そうやって懸命に道を切り開いてゆく姿が今、どこか愛おしく思えるのは、私の中にもそういう気持ちが植え付けられてしまったからだろう。
口にするしないは別として、そういう気持ちが胸になきゃ、勘九郎みたいな、本物の天才と渡り合い、創作なんか出来るわけがないのだ。
今となれば、河合さんの頑張りも、よく理解できる。あの人に才能がなかったとは言わない。面白い発想もたくさん持ってた。(今回の演出でも、監督の発想を基にしたシーンが幾つかあります)
それでも尚、自然体を封じてヒリヒリするような境地にまで自分を追い込み、妙な脳内エキスを分泌しなきゃ、とても闘いきれない、食うか食われるかのメジャーの世界が監督の主戦場だったんだ。
北斎は、誰よりも長生きして実直に創作活動に身を捧げつつ、ある時から、こう名乗り始めた。
画狂人。
自分がそうだと言うよりも、死す時まで、こうありたいと願ったのだろう。及ばずながら、その気持ちがよくわかる。
今回の歌舞伎版の『きらら浮世伝』で、私は青春グラフティを追求しようとは思っていない。むしろ、今の時代にもっと大事なことが、この物語の蔦重たちの生きざまに詰まっていると、37年を経て改めて気付き、大きく改訂している。
しかし速度制限のない一方通行、帰り道ナシの青春をまっしぐらに駆け抜けた表現者たちの、命がけの狂気、情熱は、時代を問わずに眩しく輝き、私たちを未来へと導くだろう。
あの素晴らしき狂人たちの導きに感謝しつつ、恩の倍返しをしたい。
さて
そろそろ、稽古に向かいます。
2025年2月2日、初日です。