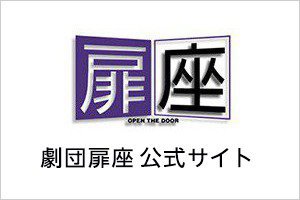きららの稽古をして思った
今、劇作家協会の運営する、戯曲アーカイブ(閲覧無料!)で公開されている「きらら浮世伝」の戯曲は、初演時のものに、20年前、扉座で上演した際、手を加えたバージョンである。初演時のものは当時、月刊カドカワ編集長だった見城徹さんのプロデュースで、角川書店から出して頂いた戯曲集「夜曲」に併録されたものである。
しかしどちらも今読めば、かなり粗い。一言でいえば、筋が通っていない。
当時かなり話題となり、この作品で私の劇作家人生も切り拓かれたはずなんだが、今更ながら、我ながら、コレで大丈夫だったのかしら?と首をかしげる。
今度、上演する「きらら浮世伝」は、2024年改めて読み直して首を傾げたところから、37年後の私が新鮮な気持ちでツッコみを入れて様々改訂し、昨年から各所で出版された、蔦屋重三郎関連の本、吉原遊郭解説書などを一夜漬けで学び直し、その上に歌舞伎座で歌舞伎俳優が演じるということを考慮して、かなり新しいものに変えている。
今回の上演に際して取材などで昔話しをするうちに、自分でも分かって来たことがある。
この粗さには第一に私の未熟さがあったのは明白である。その頃、日本史の知識も芝居の知識も圧倒的に足りてなかった。まあ26歳の時のものだし、初めてのプロデュース公演の大仕事だった上に、狂気の演出家にゴリゴリやられ、しきたりとか無視して熱く激しくと煽られ、熱病にうなされるようにして書いたので、仕方ないと言えばそれまでなのだが……
その反省の一方で、セゾン劇場という真新しい劇場がスターを集めた上に、なぜこの若い無名作家=俺に書かせて、まんま上演したのかという謎があった。
ダメだと思ったらいつでもクビに出来たはずなのだ。こちらはどこの馬の骨?の新人作家だったわけだし。
先に述べた通り、河合監督は「寛政青春グラフィティ」を映画の企画としてスタートさせていて、その時も下準備で一流のシナリオライターたちとやりあっていたはずなのだ。監督が過激すぎて多くが去ったり脱落したという事情はあったにせよ、私が書くものなんかより、ずっと筋の通った脚本も作ることは可能だったはずだ。
なのに敢えて、この若い作家に託して、暴投でも良いからとにかく速い玉を全力で投げろ、みたいな無謀なことをした。
思うに、むしろ、それを監督たちが望んだのだろう。
監督はテレビ界から鳴り物入りで映画界に進出してて、すでに名のある作家たちとは仕事をしていた。でも、そういうプロの仕事には飽きて、或いは、これでは次に進めないと考えて、敢えて得体のしれない新たな力を欲しがったのだろう。なにせ、ライバルはクロサワだった人だから。
その80年代半ば当時、私たちの居た小劇場界隈は空前のブームを巻き起こしていた。紅テントとか、天井桟敷とか、時代を席巻したアングラ世代もまだ健在ではあったが、それが更にポップに変貌して新たな若者文化の象徴として、流行り始めていた。若い演劇が、音楽やアート、映画よりも鋭くイケてるものとされた。
しかしその作風は決して理路整然としたものではなく、大人気だった野田秀樹さんの作品にせよ、鴻上尚史さんの作品にせよ、老若男女の誰もがストーリーを把握できて、セリフの意味を理解できるというようなものではなかった。この二人ともインテリで、使う言葉も高尚だったし。
では観客は何を楽しんだのか?それは意味を理解することではなく、感じることだった。笑い、ノリ、高揚することだった。そしてそれがウケていた。そこの感覚は若者小劇場ブームもアングラの作法を継いでいたのだ。
簡単に言ってしまえば、演劇は分らなくて良かったのである。むしろ、分ることは瑕疵とさえされていた。
三谷幸喜さんも我らと同世代の作家である。そして小劇団を率いていた。当時からすでにウェルメイドな世界を志向して異彩を放っていた。ただしその劇団の公演の批評として「こんな台本を読んで分るようなことをして何の意味があるのだ?これは芝居として、わざわざ見せるものじゃない」というものを私は読んでいる。
今となっては、この批評の方が意味不明となっているけど、まだ当時はそういう理屈が罷り通っていたのだ。
意味が解らない、なんて不用意に発言したら、意味に何の意味がある!と罵倒される時代だった。実際に私もそう言われたことがあるんだけど、未だにその罵倒の理由が理解できない。
だから私も、その頃の時流にのって、わざわざ分からなく書いたという話ではない。そこは単に力が及ばず、まとめ上げられたなかったのである。でもそれがウケる時代の空気だった、のかもしれない。
当時の舞台を観たという人たちが今もいる。
「中身は、ほとんど覚えていないけど、なんかすごかった。それだけ覚えている」
というような感想が多い。あの頃、最も尊いとされていた、感じる舞台にはなっていたのだ。しかもそれを、解りやすいことをやる専門の、歌舞伎役者や映像のスター俳優たちが、新たな劇場で先駆けてやったことが、おそらく画期的だった。
ちなみに、この舞台を、まだ中学生だった笑三郎さんを付け人にして観てくれたという、故市川猿翁(当時・三代猿之助)さんの感想が
「この作家はセリフに力があるけれど、骨が細いね」
細いと言うか、骨は迷走でねじ曲がっていたと思う。
その「感じる舞台」銀座に登場の立役者が、故中村勘三郎(当時・勘九郎)さんだった。
何度も言うけど、だだっ子のように無理難題ばかり言ってた故・河合監督。今となっては私は深く親愛の情を込めて、そう呼ぶのであるが、狂った幼児だ。そこにいろんなスタイルを持つバラバラの出自、個性の俳優たちが集められて、筋の通っていない脚本を一本の芝居に創り上げていく。普通なら、崩壊しても不思議ではない座組であった。
それが、今もまだ人が覚えていてくれるような舞台になったのは、
そんな無茶な監督の要求に、勘三郎という更なる化け物が、歌舞伎のスタイルを投げ捨てても、体当たりで食らいつき、ことごとくリクエストに応えて、監督の世界を実現させていったからだ。
その時の精神はピカソなんだよ。お前はゲルニカが描けるか!
みたいなダメ出しが出て、当然意味不明だから、俳優は困る。でもやらなきゃ許してもらえないから、壊れながらも何かやる。そこでたいてい病んだり、キレたりするんだが、
同じようにのたうって、クソ―と叫んで、監督と真っ向から闘いつつ、やがて勘九郎はそれを克服して、自らの表現を成し遂げてしまった。
監督のみならず、その稽古を見守る全員がオッケー!と叫ばずにいられない。そんな仕事を目の前で見せつけられたら、こまごました文句も呑み込んで黙ってその後に付いていくしかなくなる。
勘九郎のようにやればよい。出来なきゃ、黙れ。以上終わりだ。
そんな天才の荒行を目の前で体感できて、しかも、自分の書いたセリフにそういう至高の魂が込められる瞬間に出会えて、私は実に幸運だった、と改めて噛み締める。これを知ってると知らないとでは、作家人生にも大きな差があったと思う。
だから今回の きらら浮世伝 は歌舞伎座にふさわしく、多くのお客さんに分かって貰えるように整える一方で、この「感じる感覚」だけは絶対に薄めることなく、継承し、しっかりと伝えていかなきゃならぬと思う。
けど、日々稽古していて、現在の勘九郎さんが、もう生き写しで……
あの頃の勘三郎さんより今の勘九郎さんはずっと年長で、冷静で、穏やかで、たたずまいも大人なんだけど、蔦重の熱いセリフを語り出したら、先代に負けず熱く、激しく、乗り移った以上に、あの魂が、ここに甦った、と感じずにいられなくて。
なんか最近、人生の伏線回収みたいなことが、いろいろあるんだけど、この伏線回収は私の中でも極めて大事な特別な仕事になっている。
俳優がなかなか集まれなくて(贅沢な座組だから仕方ない)、本当の勝負はここからになる。
あの人たちに胸を張って、捧げられるようにしなくちゃいけないよ、マジで。