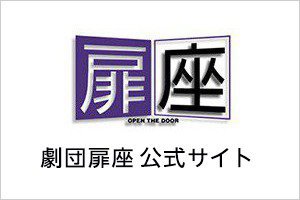靴の話
厚木ではもう2回もやったし、そろそろ、噺の中味が、漏れ聞こえて行くだろうから
これからのご見物の皆様の、興を削がぬ程度に、触れていこうかと思う。
今朝の、賀来さんの はなまるカフェ でも紹介されていた通り、
この舞台では、紺屋が、靴屋の設定になっている。
現代劇化を考える時、染め物屋って、ちょっとイメージが湧きにくいし、ましてや こうや では、何のことやらみたいになろう、と思われたのである。
加えて
個人的に実は、ここ数年、靴に凝ってるという理由もある。
職人と言って、まず思い浮かんだのが、靴職人だったのである。
凝ってると言っても、オーダーメイドなんかは、とても手が届かない、いわゆる定番メーカーの代表作みたいなのを、小遣い貯めて、ちょっとずつ買い揃えている程度のことであるが、
これが金もかかるが、道楽としての知識やうんちくの奥行きもあり、実に深いものなのである。
で
最近は、靴道楽のオヤジというのが増えてきて、
靴磨きとか、減った靴底の張り替え、修繕みたいな分野に、カリスマみたいな職人が現れ、オヤジ雑誌で、脚光を浴びたりしているのである。
靴底が減って、皮の張り替えが必要になる、なんて、目出度いことではないと思うのだけど、
そのカリスマ職人の、靴修理の店で、修繕して貰って、更に履き続けることが、その道の愛好家たちの間では、実にステキなこととして語り合われていたりする。
で
私もその時が来るのを楽しみにしている。しかし、この道に迷い込んでまだ経年が足らぬために、私の靴の底は、どれもまだ、すり減り方がまったく足らず、張り替えなんか必要ではないのである。
まだ靴底の張り替えを体験していない。
それが無念であるという、妙な具合になっている。
世の中でそんなことが起きているために、若者の間にも、靴職人とか、本格的、靴磨き職人とかに憧れて、それらを目指すという者が多数出現している。
オーダーメイド界には、すでに一流のブランドを掲げた、スター職人も多数生まれている。
皆、イギリスやイタリアで修行を積んでいる。
靴職人のステイタスは、劇的に変化しているのである。
先日、見学をさせて頂いた、南千住の靴工房の社長さんが、職人の技の継承についての難しさを語っておられた。
後継者が充分に集まらぬ、問題を。
その際に、我が国における、靴や革 というものを扱う仕事が歴史的に位置づけられてきた低い地位、という問題に触れておられた。
欧米での地位と、我が国でのそれは、長く雲泥の差があった。
それが今、急速に接近しつつある。
少なくとも、靴オタクたちの間では。
そして、伝統的な技術を持つ、浅草や千住の古い職人さんたちにも、再注目の視線が向けられている。
まあ
今回の舞台では、そういう歴史を描くのが主眼ではないので、背景として、ソフトに押さえるに留めているけど
職人の技に対する、敬愛の思いは深く深く描いたつもりである。
それは今、自分がちょっとハマっている道楽の中に、みつけた実感なのでありますという、話。
もっともさ
私の道楽なんか、いい加減なモノで
スーツ用の靴が、まったく抜け落ちてますからね。
日常的に、スーツを着用しないので、いわゆる紳士靴というのは、ほぼ無用なんだよな。
だから
幾つか買った、道楽品の中に、黒く正しい紳士靴みたいなのは、ほとんどない。
しかし、それは劇団一のラーメン通と、自称しながら、
辛いモノがダメで猫舌である、
という扉座のジョードイ君のラーメン通っぷり、と同じぐらい、致命的な欠落がある通人、マニアと言わざるを得ないわけで。
それじゃ、通でもマニアでもないよ、と言われたら、すみませんというしかない。
加藤和彦さんは、スーツなんかあんまり必要でないはずなのに、百着ぐらいロンドンの仕立屋に、オーダーメイドで作らせ、当然のことそれ用の靴も無数に揃えていたのだから。
ま、そこは比べるだけ虚しいからやめよう。
あと、靴の噺では、
劇中、靴店の娘がロンドンで修行してきた、と言ってるんだけど、
本当は ノーサンプトン と言いたかった。
ロンドンから百キロぐらいの町らしいけど
靴の聖地と呼ばれる土地はここらしい。名だたるブランドがここに拠点を構えているのである。
デニム界における、岡山みたいなものであろう。
人情噺的には、そんなの、どうでもいい知識なので、ザクっと簡単にロンドンということにしておいたけど、本当はノーサンプトンじゃなきゃダメだと、一人呟いている。