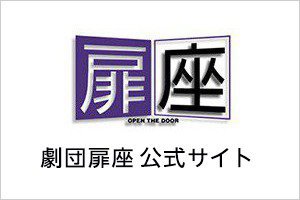きらら浮世伝 歌舞伎座二月
長く劇作家を続けて来た結果、こんなことも起きる。
1987年、私が二十六才の時に書いた『きらら浮世伝』を、2025年2月に歌舞伎座で歌舞伎公演として上演する。37年前の時は今はなき銀座セゾン劇場の公演で、私のクレジットは脚本。今回は演出も担当する。
当時の主演、蔦屋重三郎役は、十八代中村勘三郎さん、当時は勘九郎さんと言っていて、弱冠三十三歳であったらしい。
その蔦重役を今回、故勘三郎さんのご長男・当代・勘九郎さんが演じ、ヒロイン・お篠役を、次男の七之助さんが演じる。
あの頃、幼いチビ勘太郎君の姿を楽屋でたびたび見かけた。七之助さんは、まだそんな年でもなかったのかな、、
2025年、NHKの大河ドラマで、蔦屋重三郎 をやってくれるので、あからさまな便乗上演であるが、私にとって今も忘れられない記念碑のような作品、公演だったから、時が巡って、勘九郎さん七之助さん達と、きらら が出来ることが夢のようである。
他にも錦之助さん、隼人さん親子、歌六さん、米吉さん親子、芝翫さんと三兄弟の皆さんなどなど、
ご縁深き方々も……
ちなみに先日、市川笑三郎さんと会った時、私は旦那(二代目市川猿翁)とセゾン劇場で観てます、という。その時の舞台美術が朝倉摂先生で、先生に招待されたという。まだ十代半ばのサブちゃんはお付きとして旦那と並んで観たらしい。
あの舞台観て、この作家を呼びましょうと、旦那が決めたんですよ、私が歴史の証人ですと。
今思えば、二十六歳の小劇場座頭、「善人会議」の横内謙介、ミラクルな引きであった。その時は無我夢中で、何が何だかわからぬうちに、嵐に巻き込まれていったような感じだったけど、、、
ただ今回の上演で言えば、何しろ歌舞伎座で、当たり前だけど、女方さんが演じる形式。
実は2003年、新宿サザンシアターにて、扉座でもゲストを招いて上演している。蔦重に山崎銀之丞さん、お篠は木村多江さんだった。その時に初演の本にかなり手を入れて改訂上演した。その後キャリアを重ねてきた作家として、あまりに目立つ若書きの粗を直す必要があった。
今回は、それをさらに細かく検証しなおしてドラマとしての見直し、時代背景などの考察、そして歌舞伎というスタイルへの擦り合わせなど、ほぼ全体に渡って大改訂した。
今はまだ稽古前だけど、たぶん直前まで手直しは続くだろう。
なにしろ、江戸時代の事、吉原のこと等が何も分かっていなかった。まあ今もかなり適当ではあるが、さすがにその後さまざま時代劇もやって来て、歌舞伎や映画やドラマも観て、知識も得ている。
今の私が見て、さすがに、これはヤバいだろう、洒落じゃすまんだろうという部分は、思い切って手直ししている。
しかし、ここが大事なのであるが、
その作業で、舞台を小さくまとめて、つまらなくさせちゃいけない。今も きらら を覚えていてくれて、アレは刺激的だった、面白かった、という方々いるんだが、その人たちが口々に言うのは、常識を食い破って迫って来る熱さと、勢いに充ちていた。と。
その良さを失っては、意味がない、いかにその魅力を残しつつ、少し大人のドラマとして進化させるか、ここが今回のチャレンジである。
そもそも初演時、プロデューサーも演出家も役者たちも、時代考証とか、時代劇のしきたりとか、そんなことはまったく眼中になく、とにかく時代を超えた人間たちのドラマを、若者たちの熱い生き様を、観客に叩きつけるのだ、みたいな感じでくんずほぐれつして、取っ組み合って取り組んでいた。
破天荒な舞台だった。
でもそこを愛してくれる人たちが大勢いた。だから記憶にも残ったのだろう。こんなのダメだと言う人たちももちろん大勢いたけど、いいぞ、やれ!みたいな応援の声の方が大きくて、というか我々の耳に、心に響いて、まあSNSなんかない時代、
誰に俺たちを止められるんだ!状態だったと思う。
駆け出しのころはともかく、商売始めてからの 蔦屋重三郎はチョンマゲ姿に決まっているのだが、勘九郎さんは最後まで貧乏羽織に、オデコを剃らない、ぼさぼさ髪姿で演じ切っていた。しかも、ある時は舞台で暴れすぎてカツラを飛ばしてしまった。けれど、かつらなんかどうでもいいんだ、それよりも今、このセリフが大事!みたいな勢いで、脱げたかつらを舞台から投げ飛ばして、芝居を続けた。
まるでギターを投げ捨てて叫ぶ、ロッカーである。
その熱い魂は、石にかじりついても、この歌舞伎座公演でも継承したい。それが出来なきゃ、今はもう会えなくなった人たちに顔向けできぬ。
川島雄三という名監督がいる。幕末太陽伝という傑作を創り上げたのち、次は寛政の改革の時代、写楽の時代を撮りたいと支度をしている時に、亡くなってしまう。
幻しの 寛政太陽伝
それは映画界の課題として残っていたという。それ引き継ぎ、実現させようとして頑張っていたのが、「きらら浮世伝」の演出家・河合義隆さんだった。「幕末青春グラフィティ・坂本龍馬」というテレビのスペシャルドラマで大成功して、テレビ界から映画界への進出を果たしていた。BGМをすべてBeatlesの曲にしたから、大傑作だけど今、映像でそれを見ることは不可能である。
しかし奔走虚しく、映画化の実現は困難だった。で、その話に食いついたのが当時新たに建設されたセゾン劇場で、映画化の前に舞台でやろう、という展開になったのだ。
新たな文化の拠点として生まれた劇場で、とにかく新しく画期なことをやることを使命とする劇場だった。
ちなみに川島監督の夢を継いで実現させたのは、幕末太陽伝の主演だったフランキー堺氏で、きらら より後で、真田広之さん主演の映画「写楽」として結実した。
この時、すでに河合さんは自死されていた。
勘九郎さんは、この河合監督に心酔していた。というか彼を深く愛していた。
きらら の後に、非常の死を遂げたことも、我々には、驚きというよりも、ああやっちまったか、という溜息がこぼれる様な、非常にして、無茶苦茶な人であった。
(非常の死 とは平賀源内の追悼で、杉田玄白が贈った友情の言葉です)
だがその無茶苦茶に、哀しみや、無垢な思いが確かにあり、それが心に響く人には、たまらなくその虚勢や、無頼が愛おしく感じられたのだと思う。
その時の私にはまったくそんなふうには思えなかったけど、むしろ呆れて狂人だと恐怖したけど、河合さんが亡くなった歳も遥かに超えて、こうしてまた青春と対峙し、その表情など思い出すと、
懐かしさと共に、その破天荒の奥にあった孤独のようなものを、感じずにはいられない。
ああ、今、会いたい、と思う一人だ。
何度も語ったことだけど……
はじめて会ったのは下北沢の飲み屋「おっとっと」の奥座敷。今の劇小劇場の1階部分にそれはあった。
私とセゾンのプロデューサーと、河合監督と、なぜか岡森諦もいた。(初演に 滝沢馬琴役で出演)
初対面であいさつすると、監督はニコニコしつつ。
「君天才?」という。
わたしが「さあ、どうですか……」と頭を掻いたら、
「天才じゃないなら帰って、才能ない奴と絡むと、俺の才能が泣くから」
コレ、実話だからね。
面白過ぎるんで「東京サンダンス」という下北沢の青春グラフィティ作品(トニセンの3人出演)で、まんまワンシーン描かせて貰っている。
こんな調子の人なので、私が会ったこの時までに、3、4人のシナリオライター、作家が激怒、呆れて辞退、神経を病んでドクターストップなどして、打ち合わせ段階で消えていたという。なかにはかなり大御所もいた。
結論から言えば、こんなとこにいきなり投げ込まれて、それでも生き残って
きらら浮世伝 を上げたんだから、横内てなかなか大した奴なんだよ。
まあ、劇場もこんなこと繰り返してちゃ仕事が進まないんで、途中で死んでもいい若手をとにかく戦場に送り込んで一歩でも前進させようと、必死で私を守った部分もあろう。
とりあえず、取り掛かろうということになったが河合義隆は意地悪だった。
それまで集めた資料があるのだが、それは君には見せない、という。
自分で調べなきゃ、身にならないからね。
それが前年の初夏あたり。
※ただし、これにはオチがあり、その後、河合さんの助手で主にリサーチを担当していた助監督さんが、隠す必要ないよな、俺が調べたんだし、と言って全部見せてくれました。
今のように検索なんて、魔法のない時代。放り出された私に出来たことは、神保町の古本屋で探すか、図書館に行くか。
しかも、蔦屋重三郎 なんて名前は一般にまったくしられていなかった。
せいぜい、写楽 は誰か?という論争の中で、写楽を世に送り出した新参の版元として話題に出るぐらい。
当時は、写楽の正体探しが流行っていたんです。そういう本はたくさんあった。
歌麿説、京伝説、十返舎一九、平賀源内、北斎説、蔦重本人……
だから私の「きらら浮世伝」も誰が写楽なのか、何のためにこんな絵を出したのか、ということが筋立てのなかの重要な部分になっている。
川島雄三監督は写楽とは…… 消極的なレジスタンス みたいなことを言ってて、
河合監督は 弾圧された人々の歪んだ顔だ、と言ってた。
河合さんはフジテレビでADから身を起こしてディレクターに上り詰めた人で、当時、テレビ局でも思想弾圧的な事があり、才能ある先輩たちが次々に排泄されていったのを目の当たりにした、と語っていた。
まあ、今回はそこらへんも、その後の私の人生観とか、文化芸術に対する思いとか、名もなき民たちへのシンパシーなんかを含めて洗いなおして、私独自の意見として考え直して改訂している。
最初の時は、ちょっと河合さんに煽られ過ぎて、革命チックになり過ぎていたと感じている。35年越しのテーマ修正である。
さて写楽だが、今は、阿波の能役者、斎藤十郎兵衛、という人物で決着はついたとされている。
そう書き残された記録は元々あったが、その人物が実在したかどうかが、ずっと疑わしかった。それがついに墓が発見されて、論争に決着が着いた、のである。
が、さてね……
絵の上手い役者さんて、たしかにいるけど、突然、そんな新人担ぎだして、あの絵描かせて、ご改革の最中、わざわざ危険犯してビッグサイズの錦絵にまでして、それで売れると思ったのかね、あのくせ者の蔦重が……
やっぱり何かの特別な思いはあったんじゃないかな……
当時知られていなかった、蔦屋重三郎 に目を付けた、映画監督たちの直感に、
そこは私も同調して、文化芸術に命を賭けた者たちの熱い魂、メッセージを今も感じていたい。
それは生命維持装置なんだ。
江戸時代のアーティストたちが、すでに、そう叫んでいたんだと。
今まさにこの時、本屋さんに行くと、
蔦屋重三郎 関係のものが山積みですよ、そこではもはや、写楽も歌麿も脇役だ。
あんまり深く調査されて、世の人々が皆がそれを詳しく知ってしまったら、いろいろ考証をすっ飛ばしている、わたしらの きらら には都合がよろしくないんだが、
重三には、ついに君の時代が来たな、と祝福したい。
絵も本も、蔦屋たちの時代の前には、複製の難しいものであったのだ。
絵はもちろん一点物が基本だったし、読み物も、源氏物語とか古今和歌集とか、
一冊ずつ書き写すしか、手はなかったわけだから。
それが蔦屋たちの時代に、刷り物という物が一般化して、貧しい人にも手にすることが出来るようになった。長屋にも美しい錦絵が飾れるようになった。歌麿の絵も、そば一杯分の値段で買うことも出来たと言われている。
それはコンピュータが一般化して、誰もが同時に情報や知識を共有できる時代になった、今、まさに現代の変化に重なるものなのだ。
三十七年前の初演時には、そんな視点はまだなかった。
そういう意味で、今こそ、蔦屋重三郎なのである。
そして特筆すべきなのは、実は、刷り者の熱心な読者に、花魁たちがいた、ということ。
自由のない彼女たちが、束の間、想像の翼を広げて、心の自由を得ることが出来たのは、
絵や読み物に触れる時だけだったかもしれない。
吉原では、売られてきた娘たちに、読み書きを教え、三味線や舞も習わせた。だから、貸本屋だった蔦屋が担いでくる刷り物は、
確かに 生命維持装置だった。
人身売買であり、人権無視の非道の行いである。だから今、吉原というだけでアレルギー反応も巻き起こり、
吉原炎上 となるのだけど。
われわれの きらら浮世伝 には吉原は描くべき場所なのである。
2025年から、もう少し頻繁に、この日記を書き綴っていきたいと思います。
遺言というのは大袈裟だけど、もう会えなくなった人たちの魂を受け継ぎ、受け渡してゆくためにも。そういう責任もあると感じて、、、、
よかったら、読んでみてください。