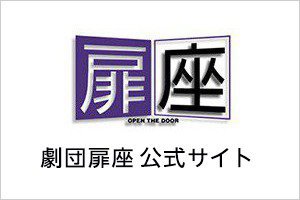仲間たちが来て
週が明けて、芝居仲間たちが忙しい中を駆けつけて来てくれた。
マキノノゾミ氏とか、茅野イサム氏とか。
思えば、ふたりとも、つかこうへいドップリチームだ。
別につかさんが仲立ちしてくれたワケではないが、二昔前以上になる、彼らとの出会いも、つかさんの影響の下のことだったなあ、と思い起こす。
つか観てました、で分かり合えたんだ。
マキノさんが言ってたけど、
あの頃は、
平田満が「ママンが死んだ」と言うと、劇場が揺れるほど皆、笑ってた。
確かに「太陽が眩しい」というセリフにも、私も声だして笑った記憶がある。
ホント程度、高かったんだねえ、あの頃の小劇場文化は。
今、若い劇団員に言っても、なんのことやら、以上の虚しいハテナマークしか、浮上してこんだろうぞ。
しかしもっとも、その時、確か私はまだ「異邦人」も読んでなくて、つまるところ、周りのお兄さんお姉さんたちの雰囲気に呑まれて、笑ったのであろうと思われる。
そんで慌てて、文庫買って読んだものよ。
そして2度目に、熱海を観た時には、そのセリフを待ち構えて、笑った、と思う。
劇場は高度な学校でもあった。
「生きとし生けるものの無常必滅こそを尊び、枯淡の境地に生きる芭蕉は、親父とは真逆の、精神世界の巨人だった」
これは「つか版・忠臣蔵」の小説に出てくる表記で、そのままセリフにして、今、宝井氏が、熱く語っているが
こんなセリフ、当節の芝居では、大学教授役でもしゃべらんだろう。
だが、なんかそれらしく、ゴージャスで、脳の一部を刺激される、気がせんか。
例によってロビーに立っているが、今回は同年代のオッサンに語りかけられることが多い。
みな、喜んでいてくれてるのがとても嬉しい。
そんなに数は多くないが、ちゃんと来てくれてるんだな、あの頃、ぎゅーぎゅーの劇場で隣り合い、つかの言葉にかじりついていた仲間たちが。
たぶん、それぞれに「赤色エレジー」とか「リフレインが叫んでる」とか聞きつつ、来し方を思いやっているんだろう。
「セイリング」なんかワシ、15歳の処女作のエンディングテーマだからね。35年前のこと。
この曲も、田中邦衛さんが出てた「ヒモの話」で初めて聞いて、先輩からタイトルを教えて貰い、友人にレコードを借りて、覚えたものよ。
田中邦衛が、この曲バックに踊ってたんだからね。
六本木の、まだビルになる前の、古い俳優座劇場で、私はその舞台を観ていた。
それが人生初、六本木であった。
なんか、冴えない田舎町みたいなとこだったと記憶してるけどね。当然バブルのはるか前のことだしな。
だからコレ聞くだけで、ワシは泣けてくるんだ。いろんに思い出が詰まってて。
「幕末ガール」の音楽監督・深沢桂子さんも昨日来てくれて、選曲良かった、泣いたよ、と言ってくれたけど。
それで歳がバレる。
でもコレ、当て込んだのは、私と音響・青木タクヘイだが
すべて、つかこうへいの舞台で流れていた曲である。
舞台の横で、シンガーが歌うのも、つかこうへいの舞台で、観た光景の再現だ。
あの頃の歌手は、大津あきら氏だったはず。
舞台で役者がセリフしゃべってるのに、そこに生の弾き語りを重ねる、ってワケが分からん演出である。
でも、それがカッコよかった。
しかしね、思えば、歌舞伎なんか、役者の横で長唄とか、義太夫とか、ずーっと歌ってるワケで、
コレも今の私から観たら、ああ、芸能の原点演出なんだと、深く納得するのである。
しかも、今も歌舞伎で使われているのは、江戸時代のヒット曲だって、笑三郎先生が「歌舞伎ゼミナール」で教えてくれた。歌詞も、中味には直接関係ないけど、耳障りが良いから使うとか、そういう感覚の演出だって。
江戸時代のユーミン、マライマックスで流してる状態だというのだ。
まさに、つか、ではないか。
というか、順序的には、
つかが、歌舞伎なのである。
もっとも、ワシがつかさんと歌舞伎が同じだと言っても、つか周辺の人たちはあんまりピンときてくれない。
と言うのも、生前、つかさんが歌舞伎に対して、よく噛みついていたかららしい。
つかさんが、許せなかったのが、血筋とか一家一門に拘る歌舞伎界の有りようだったようだ。
血筋のないモノは出来んのか。やっちゃイカンのか。
そこには深く憤っておられたらしい。
だから、つかさんと歌舞伎は遠く、というか、むしろ敵チックなモノとされていた。
実は決してそんなこともなく、右近さんも笑也さんも、その血筋にはない立派な歌舞伎役者なんだけどね。
そこまではご存じなかったのだろう。
つかさんらしい、発言ではある。
そして、そんなつかさんが好きだ。
頑張ってるヤツに、チャンスやらんでどうすんだ。
皆が、大きなモノに、ひたすらすり寄る時代だから、なおさら、その言葉が優しく頼もしいよね。
それはともかく、
もし、そこらの理屈抜きにして、純粋にエンゲキ的なテクニックとして、つかさんが歌舞伎にもっと接近して、摺り合わせを試していたら、私は「つか歌舞伎」というべきものも、誕生しただろうと思う。
前をしっかり見て、瞬きせずにしゃべれ、とつかさんは演出でよく言っていたそうだ。
相手役をよく見て、とかじゃなく、とにかく客の方見ろ、って。
そして、まぶたも筋肉だから、鍛えれば、ずーっと開けてられるようになるんだ、って。
前見て語るのは、歌舞伎の鉄則だし。
目ん玉、ひんむいて、カーッと見開くのは、見得ってカタですからね。
歌舞伎なんだよ。
今日はプチ、つかこうへい論でした。
台風さん、お願いですから、こんなに頑張ってる私たちをいじめないで。