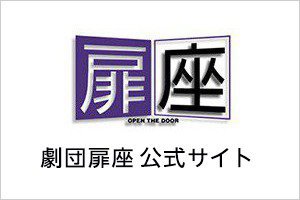弟子
つかこうへい氏の舞台を見なかったら、私が芝居の道に進むことはなかったろう。
そして、その後、三代猿之助(現猿翁)に出会わなかったら、演劇を生業にすることは出来なかったろう。
幸運にも、三十歳ぐらいから芝居で喰うという、奇跡的な営みを続けてこられた私であるが、
そのお金になった、芝居書きや演出技術のほとんどが、三代猿之助から教わったものだ。
それは劇団の作品、アイドルの芝居、についても。
プロとしての仕事となる、大切なところは、猿之助から伝授されたと、つくづく感じる。
講義を受けたワケではなく、脚本家として出会って、その仕事の中で、プロデューサー兼演出家・猿之助の求めるモノを汲み取り、表現しようとして努めて来ただけであるが
そのなかで自然に、猿之助の美意識、リズム、理念などを吸収していったのである。
歌舞伎役者になりたかったら、私と生活して、歌舞伎漬けになるのが早い、とよく3代目は語っていたけど
スーパー歌舞伎のような何年にも渡る大仕事で、長い時間、語り合い、食事し、時に遊ぶ中で
私も猿之助漬けになり、感化された。
特に大きな劇場では、この猿之助スタイルは極めて有効だ、と思う。
大勢の、加えていろんなお客様を、満足させるため、しかと芝居をお見せする、という技術のアレコレ。
簡単なようでいて、これはなかなか難しい。
教えてくれる人もそういない。
そもそも、そういう大仕事で確たる実績のある人、というのが稀少なんだから。
この出会いは、幸運だった。
そんな結晶が、今大阪、新歌舞伎座でやっている
『新水滸伝』である。
この作品は、初演時から療養中の師に替わり、
演出の現場仕事を、ほぼ私と右近さん、猿弥さんでやったんだけど
猿之助スタイルという共通項を我々はしかと持っていて、ケレンの見せ方にせよ、音楽の使い方にせよ、
イチイチ摺り合わせなくても、自然と、こうなるべきでしょうというのを感じ合っていた。
それは脚本的にも、演出的にも。
この時、
私も、この人たちと等しく猿之助学校の生徒なんだと感じたものである。
実は、いろんな仕事で、猿之助演出を使ってきている。
愛媛の『幕末ガール』『げんない』
『つか版・忠臣蔵』でさえ、つかさんへのオマージュでありつつ、細かなところでは、猿之助理論・スタイルで演出している。
もう染みついていて、気付けばやってるというか。
今、取りかかっている『浪花阿呆鴉』に至っては、これはもう9割、猿之助型である。
集まった役者たちに、歌舞伎の演技は出来ないから、素人目には、猿之助スタイルと言ってもたぶんピンと来ないと思うけど、
猿之助さんのやった、オペラの演出とか、歌舞伎以外の俳優の作品の演出などと見比べたら、一目瞭然だろう。
明らかに、弟子の仕事だ。
そもそも演出とはすべて何かのパクリなもので、盗作、パクリという概念はないのだけど、
正々堂々、猿之助パクリである。
ただ、私は一度も公式な弟子になったことはなく、猿之助さんからもそう呼ばれたことはない。
というか
もったいないことに、常に友人、もしくはブレーン、時に共犯者という立場で、接して下さっている。
今回の『新水滸伝』のパンフの、猿之助さんのメッセージには、涙がこぼれた。ひたすらひたすら感無量。
でも、これから私は敢えて、名乗ろうと思う。
私は三代猿之助の弟子であると。
役者ではなく、クリエイター・猿之助の。
実はこのクリエイターという立場が、三代猿之助を語る上で、時に軽視されている。
役者として大きな人であることは、間違いじゃないけど、その看板が大きすぎ
実は希代のプロデューサー、演出家、クリエイターであることがしかと語られていない。
この人の創造力に間近で接してきた者としては、
その独創性、美意識、豊かな知識と表現技術は、世のどんな天才クリエイターと比しても、劣るところのない人だと思っている。
しかもそれは歌舞伎に留まることなく、いろんなジャンル、ムーブメントに影響するチカラを持つモノだったと思う。
実際、エンノスケ歌舞伎、スーパー歌舞伎に影響を受けた劇作家、演出家はもちろんのこと、ロッカー、美術家も数知れずいるのである。
でもその部分が語られることは、意外に少ない。
ま、それを語り、次世代にこの貴重な財産をつないでいくことこそ、私の使命でもあろう。
正直、弟子を名乗るには、まだ足らぬ部分も有りすぎだし、なにより不遜であるが
新歌舞伎座で二ヶ月連続、作品を上演させて頂くというこのタイミングで、決意したくなった。
師の名を汚さぬようにやっていきたい。
勝手ながら
私は猿翁の弟子です。