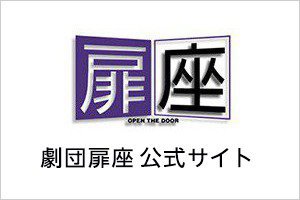朝倉摂先生に感謝
つかこうへいさんが、芝居の扉を開いて下さったとすれば
芝居の奥深くに招き入れて下さったのは、三世市川猿之助・現猿翁さん である。
そしてその猿翁さんが新しい書き手を捜している時に、私をご紹介下さったのは、舞台美術家の朝倉摂先生であった。
今はなき銀座セゾン劇場でやったメジャー・デビュー作『きらら浮世伝』の台本を、猿演さんに届け、読んでみてと推薦して下さったのだ。
猿翁さんは、先生を口入れ屋・幡随院 長兵衛 なんて呼んでいたものだが。
先生の演劇・美術界での交友は世界に広がり
人と人、作品と作品を、引き合わせ、繋げ。
生きて活動しておられることが、そのままコーディネイトであり、プロデュースであり、アートだった。
そんな輪の中の片隅に、先生のお引き立てで加えて頂けたこと、この上ない光栄であった。
扉座では『アゲイン』の重厚な、お屋敷のセットをデザインして頂いた。
一瞬にして廃墟に変わるマジック、そしてその廃墟が、元の屋敷以上に美しく見えたデザインは、希代の天才・朝倉摂ならではのものだったと想う。
大劇場でも小劇場でも、差別なく、新たな価値を創り出すことを優先された。
実際、この巨匠に、僕らもたいしてお支払いできていない。
でも、ふたつ返事で引き受けて、お客さんまで呼んで下さった。
その代わり、創るモノに対してのこだわりは厳しく、私の作品も、誉める時は、手放しで、いいねえ、と言って下さるが、違うと思うと
あんたらしくないよ、もっと己れを貫き、過激にやんなさい、とわざわざお電話までくれてコレは本気で叱って励まして下さった。
私を本気で怒ってくれた、先生というのも、演劇界では数少ない。
その朝倉摂さんがお亡くなりになった。
大親友で、よく軽井沢のおもだか別荘にも泊まりがけで仕事したり、遊びに来られていた、藤間紫さんの葬儀の時、黒ずくめの喪服の中、ひとり紫の革ジャンと真っ赤なヘアスタイルで颯爽と現れ、お焼香された姿の見事さは、確かこの日記で書いた。
それを向こうから見てる紫さんの笑顔が、目に浮かぶようだった。
紫さんが逝かれた日も、東京の桜の開花日だった。
もしかして、おふたり示し合わせでもあったのか。
そういえば朝倉摂の舞台に、桜がよく似合ったな。
コスモポリタン的な教養と、ご自身長唄三味線をお稽古されるような、日本情緒の融合を粋に仕上げられる方だった。
そんなことを悲しんでいる時、もう一人の恩人である、劇作家・清水邦夫さんの奥様、松本典子さんの訃報も届いた。
そして思い出す。
先生のお引き合わせで、私が猿翁さんと初めてやった仕事である、
パルコ劇場・二十一世紀歌舞伎組公演『雪之丞変化2001年』の初日、
清水さんと松本さんご夫妻が見に来て下さって
「面白いわよ」と声を掛けて下さった。
その時、朝倉先生も美術デザインで、一緒だった。
ほんの短い立ち話だけど、
何だか、強く背中を押して頂いた気がした。
まだ何者でもない若造が、居心地悪げに、そこに怯えていたはずだ。
清水さんは、高校演劇のコンクールの審査員で、私の処女作を強く推して下さった。初期の頃、書き上げた戯曲を不躾に送りつけたりしていたのを
丁寧に読んで下さり、感想を認めて下さったりしていた。
清水邦夫さんは、恩師である。
もう20年以上前のこと。
でも、私もまだ若く。
この世界で生きていくため、必死に道を拓いてた頃だから、そんな一瞬、一言が鮮明に残っている。
松本さんのあの独特の声のトーンとともに。
ご冥福をお祈りします。
何だか思い出話ばかり。これが歳を重ねると言うことか。
でもね、知ってる者が語り継がなきゃね。
先人たちの素晴らしさを。