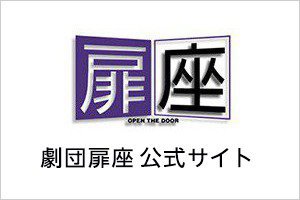九州戯曲賞
土日で、福岡に行き、
大野城市の まどかぴあ で選考会。
松田正隆、土田英生、中島かずき 氏らと私。
中島さんが、こういう場にいるのが、とても珍しかった。
出身の九州のことならばと、引き受けたんだとか。
中島さんは、エンタテイメントの作家だけど、極めて理論的な書き手である。テレビのインタビューなんかもしたこともあるので、それは知っていたけれど、
今回の審査会でも、極めて緻密に作品分析をなさっていた。劇作家協会にぜひ欲しい人材だが、なにしろ忙しすぎて、大変なのだ。
いまだに出版社のサラリーマンも続けておられるのである。
まあ、久しぶりにお会いして、ゆっくり話せたから、今後のチャンスを探るとする。
さて、今回の特色は、応募作も、審査員もエンタテイメント系というか、大衆傾向の偏りが見えたことだ。
前衛チックなのは、最終候補の中でも一作で、審査員でも、土田さんは、どれもやるコウモリ派だろうが、はっきり先鋭的なのは、今回のメンバーでは松田さんだけだろう。
斉藤憐氏いうところのアンチテアトロ派が多数を占める、劇作家協会の布陣とは、ちょっと違う並びなのであった。
で、
そういう先鋭的な作品(福岡の宮園瑠衣子さんの「春、夜の暗号」)を、松田さんが強く推して、援護し、残る3人が、そういうふうに読むものなのかと、びっくりしたり、感心したりというシーンが、あった。
んで、こういう論議がすこぶる楽しかった。
はじめは、得体が知れないと思ってた作品が、松田さんの解説を聞くうちにだんだん好きになりはじめたぐらいである。
しかし劇的な逆転は起こらず、
大賞は、この3人が推して、松田さんも次点で推した
「白波の食卓」という佐世保の森馨由さんが書いた作品に。
浜辺に建つ家が舞台で、精緻なセリフ劇である。
でも、エロスとか、生と死とか、自然とか、が ちりばめられた生きた人間の営みが愛おしい秀作であった。
惜しくも選に漏れた残りの三作も、それぞれに実際に上演されているもので、人を引きつける魅力を持つものだった。
レベルは高かったんじゃないかと思う。
ただし、ちょっと冒険心というか、野心には欠けた傾向があるかなと思う。
中島さんは、どうしてこう、無難に話を収めようとするんですかね、やっぱりお客さんが、我慢が効かなくなってるからでしょうか、と言っていたが。
確かに、人物の衝突が少ない。
ぶつかる前に、もしくはぶつからずに、思い合うようなことで、分かり合ってしまうことが多いんだな。
元来、ドラマは、そのぶつかりをこそ書くはずのものなのにね。
もちろん、単純なぶつかり合いに、もう飽きた、あるいは、それじゃ何も変わらないんだと悟った ということかもしれないが。
ではドラマはどこに行くんだ。
これは私らにとっても、たぶん課題だろう。
いつもそうだけど、こういう審査は、すべて自分に強く跳ね返ってくる。
この時も、半分ぐらいは自分の作品のことを考えつつ、人の戯曲を語っていた。
審査の後は、最終候補者たちも交えて宴会を。
その後、中島さんが、お昼頃から語っていた、薬院のラーメン屋に。
真夜中ラーメンなんか食べたら、もういけない歳なのに。
熱いどんぶりがぬるりと滑り落ちそうな、コテコテ豚骨。
しかし、さすが巨匠がこだわる一杯で、意外にあっさり美味しかった。
おまけに、奢って頂きました。
ごちそうさまです。
ともあれ、九州戯曲賞、これからの発展を祈るばかりである。
スポンサードしてくれた、元祖明太子の、ふくや 偉い。
まどかぴあも 偉い。
ここから大傑作が、や 人気作家が生まれて、
いつか伝説として語られることを期待しましょう。