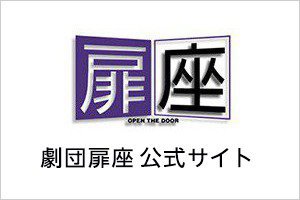鬼の母親
何度も再演を重ねた、新羅生門 であるが、鬼の母親サエは、初演に、客演の青木菜々 さんを迎えた以外は、中原三千代か、伴美奈子が、そして茅野版では、今、私の演出助手になっている、田島幸がやってきた。
皆若く、当時声優としても活躍していた、客演の青木さんも、20代であった。
今回、初めて、実際に母親と言える女優さんに、演じて貰っている。
黒テントの ヒロイン、新井純 さんである。
せんがわ劇場の芸術監督、ピーター・ゲスナーが、話を纏めてくれて実現した。
これが私的にも、とても新鮮である。
もうやり尽くしたと思った、新羅生門 で、実は大事なことをやり残していたのだと知ることとなった。
鬼の母親役は、この芝居の中で、異質の人だ。
芝居全体が、鬼ごっこになっている、遊びの多い、いわゆる小劇場全盛時代の作品なのだが
この母親だけは、その遊びに加わらずというか、加わりようがなく、ひたすらに鬼の息子を愛し、同時に息子を鬼に生んでしまったことの苦しみと、向き合い続けている。
だから
オーでションなんかすると、若い女子までが、このサエのセリフを選んで、読んでいたりする。
演技力を発揮するなら、この役しかないと、思うのであろう。
もちろん、若い女子に 簡単にやりきれるものではなく、ほぼ玉砕であったが。
にしても、それを書いた当時の私は、まだ20代であったわけで、あくまでも若い役者が演じるという前提で書いたモノだ。
だから、同世代の劇団員で、やることに、疑問を持たなかったのである。
が
今回、新井さんという、特別の存在感を持つ、ベテランに演じて頂いて
滲み出る母性と、重ねてこられた経験の深さが支える、筋の通った透明感みたいなもの が、この作品の可能性を、大きく広げていることに気付いたのだった。
それは、そういう大人の芝居が出来るように、若き日の私が、ちゃんと書いていた、ということも含めてな。
洗濯女を演じつつ、伴が、洗濯の手を止めて純さんの芝居をじっと観ている姿がとても印象的である。
洗濯女やってと頼んだら、今サラすか、みたいな反応だったのが
サエは 新井純さんにやって頂く予定と告げた途端、それはぜひ出して下さい、おねーげーしますと、手のひらが返った。
ずっとサエを演じてきた、伴はたぶん、その名を聞いてピンと来たのであろう。残されていた サエという役の可能性にも。
その姿は、いつかもう一度、この純さんの芝居を観た後の伴で、新羅生門 やってみたいなと、思わせてくれるものだ。
にしても、純さんは、可憐な人であった。
何しろ、アングラの牙城、黒テントの、ヒロインだった方なので、ちょっと身構えておそるおそる、付き合いだしたというのが正直なところであったのだが。
若い頃アングラの先輩は、みんな敵だと思って避けて通ってきた身だしね。
しかし、昔は知らぬが、今目の前にいる純さんは
元、宝塚の娘役かと思うような、立ち居振る舞いの美しく、重ねた年齢の中にも、華やかさを漂わせる、女優さんである。
もっとも、ちょっとした、瞬間に、風にされされたテントの中の絶叫を彷彿とさせる、鋭い視線と、ドスのきいた声が響いてくる。
そんな時、ああ、この人の中で芝居は、重層的に折り重なっていると、感動する。アングラでもなく、新劇でもなく。
アングラであれ、元宝塚であれ、元四季だって、小劇場上がりであれ、生き残ってきた人のなかに、その地層はあり、それを観ることは、雑多な演劇が混在となって、今に繋がる我が国の演劇の、有る意味贅沢な醍醐味だと、
私は思う。
そして、その重層的な新井さん演じるサエの有り様は
この世の善なるを真摯に祈りつつ、その反面、鬼を生んだ宿命を呪い、静かな佇まいの中に、修羅の葛藤を抱えて鬼婆として生きる
サエそのものに極似している。