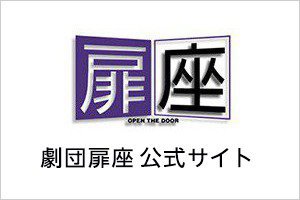ジャージか、タキシードか
つかこうへいの世界は、極端である。
たとえば衣裳は、ジャージか、タキシードか。
初演の時、岡森が出して貰った『幕末純情伝』では、新撰組は、みんなジャージ姿だった。
カツラは当然のこと、羽織袴さえ、着けてなかった。
関東の田舎の貧しい若者たちが、突然、刀持たされて、京の警護役にされたのが、新撰組 という解釈で
まあ、機動隊員とか、自衛隊員みたいな感じだろうか。
貧しい若者はジャージなのである。
ジャージでは刀の鞘もぶら下げにくいから、隊士隊たちは抜き身で刀を持っていた。
岡森が、近藤勇役で、龍馬かなんかに、
「お前、鞘は、ないのか」とツッコマれ
「あ、あのケースは、きれいなので家に飾ってます」とか言っていた。
でもそれで、違和感はなく、ああ、新撰組なんだなあ、と思ったものよ。
それが、クライマックスで、それぞれに出世したりすると、今度はそれがタキシードになる。時にソレは白タキだったりする。
進化途中の、ジャケット&パンツなんて世界はない。
バリっとする時は、一気に正装。
一説では、その時、新撰組の役者たちにはトランペットも与えられて、いきなり整列して吹け、と命じられたという。
さすがに、ガッツだけで音の出るようなモノではなく、トランペットは回収されたとか。
とにかく
ジャージか、タキシードかでなのだ。
でなぜか、坂本龍馬が、網タイツとガーターベルトで出てきたりする。
その時は、西岡徳馬さんが龍馬役を演じていて、
真っ赤なブラとガーターベルト姿で、日本の夜明けゼヨ と叫んでいた。
それを観て、ああ龍馬だな、とは決して思わなかったけど
意味はわからんが可笑しくて、やたら派手で暴走してて、それがつかこうへいの龍馬像だった。
今回はそこら辺も、踏襲してある。
ガーターも買わせた。忠臣蔵なのに。
とにかく普通の時代劇とはワケが違うんだ。
つか版 なのである。
そもそも、テレビ版では、冒頭部分で
これは時代考証などは一切関係ない、現代のドラマである。
と断ってはじめている。
で、なぜか、松坂慶子さんが、網タイツで変なダンスを踊っている。
つかさんは、とにかく網タイツが好きだった。
まあ、男子は皆たいてい、好きなんだけど、
そこも、今回はきちんと踏襲している。
ドラマとしての必然性はまったくない。
つか、だからやる。
脚を磨けと、これは、春先から女子たちに命じておいた。
その一言で、往年のつかフアンなら、何が起きるか了解できるが、知らない若者たちは、意味が分からなかったのだろう。
なんで網タイツよ。
それで若干磨き損ねた者もいるみたい。油断である。
演劇をナメるな、ということだ。
そしてその網タイツを、ラッキィ池田さんがわざわざ昭和テイストで振り付けてもくれている。
でもそうやって、そんな『つか様式』を、徹底的に真似して追求すると、つかこうへいの芝居というのが何であったのか、
よく分かってくる。
ドラマの組み立て方も、まずそれらの演出ありきで考えると、その構造が見えてくる。
そんで、やっぱりつかさんは、時代の扉を開いたのだなあとしみじみ思う。
どんなふうに開いたのか、その構造とは何なのかとか、
そのアンサーは、この舞台を観て頂きたい。
とかく印象が激烈なので、流行廃れの波をモロにかぶり、一見、時代遅れ感が漂うかもしれないけど
今観ても、新しいなと、思うところがたくさんあるはず。
私なんか、つかワールド発掘&伝導隊として、ここからスタートしても、あと20年ぐらいキッチリと、業界でやっていける気がしてきている。
未だにシェイクスピアで食ってる人が、この世にごまんといるように。
新解釈ではなく、あくまでも、正しいつかこうへい追求の舞台である。
しかし、そこで私たちは更に新しい世界に出会っている。
今日から照明の仕込み。
照明と音響は、つか世界の命だから、とっても大事ね。