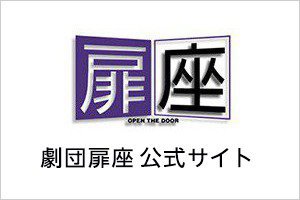恩人
我々にとって恩人はあまたいるが
幻冬舎の見城徹さんには、返しきれない、ご恩がある。
そもそも、私と岡森を、つかさんと引き合わせて下さったのも、見城さんだ。
当日お配りしている、パンフに書いた、25年前、帝国ホテルでの初対面の時である。
見城さんは、当時、カドカワの編集部におられた。
つかさんの直木賞作『蒲田行進曲』の担当でもあられた。
つかさんのエッセイにも、よくその名は登場していた。
伝説の大ヒット雑誌『月刊・カドカワ』を起ち上げられた頃ではなかったか。
当時・善人会議といっていた、我々が初めて『紀伊國屋ホール』に進出した時のこと、
宣伝しなきゃ、客席が埋まらんということで、当時、広報担当だった、岡森と手分けして、
新聞社や雑誌社など、飛び込みで、記事にして下さいとお願いしてまわった。
でも、どこもかなり冷たくて、我々は苦境に立っていたのだけど、
岡森が、飛び込んだのが、見城さんの編集部だった。
そこで興奮し、想いばかり先走る、岡森が、
「グワグワグワ、パフパフ」と意味不明なことを、いきなり叫んだのを、面白がって、
「一回落ち着け」となだめ、ヤクルトを飲ませてくれた後で、じっくり話を聞いて下さったのが見城さんだった。
もちろん、岡森的には、意味のあることを言っていたのだが、
まだ滑舌も悪い頃であった上、何しろ興奮してたので、口がまったくまわらなかったのだ。
たしか岡森は20社近くを担当したが、ちゃんと話を聞いてくれたのは、見城さんだけだった。
見城さんは、ヤクルトで落ち着いても、論旨のまとまりを欠く岡森の訴えの、その意味はさておき、熱い気持ちを深く理解して下さった。
そしてその場ですぐ、知り合いの編集者などに電話をかけてくれて、我々の公演の告知を掲載するように頼んで下さったのである。
たちまち、我々の公演の告知がドーンと増えた。
そのなかには、門前払いだった、出版社などもあったのだ。
その時のご縁でその後、岡森は、月刊カドカワ編集部で、しばしバイトまでさせて頂いた。
今日は 山田詠美さんとこで、原稿待ちしたとか、よく言ってたな。
しかし、とにかく、キッカケは無謀な飛び込みであり、そんな若者の無謀を、受け止めて下さったのが見城さんだったのである。
もっとも、その時はまだ見城さんは、我々の作品はご存じなくて、紀伊國屋の本番で初めて、我々の作品を観て下さった。
『夜曲』であった。
これを、とっても気に入って下さった。
「君、天才だよ」とおだてても下さった。
そして売れるはずのない戯曲集の出版までして下さった。
だから「夜曲」は角川出版で、五千部も刷って頂いた。
その本が出来上がった時、六本木のすっごいステーキ屋で、ご馳走になったんだが
そこに行く前に、カドカワの編集部で出来たての本とは別に、一冊の本をプレゼントして下さった。
映画についての、評論本だった。
今ここで、ここだけ読んで、コレが僕からのはなむけだ、とおっしゃって。
そこには『ベルリン天使の詩』と『ラスト・エンペラー』のことが書いてあり、
どちらもテーマが、人間の回復だ、みたいなことが難しく書いてあった。
そして「OPEN THE DOOR」というエンペラー・溥儀のセリフを、理論のキーワードにしていた。
その後、劇団を改名しようと思い立った時、思い出したのが、この言葉だったのだ。
だから今も、うちのロゴには、この言葉を入れてある。
語り尽くせぬ、ご恩と思い出がある。
その見城さんが、先日『つか版・忠臣蔵』を観に来て下さった。
のみならず、心温まる、メッセージを残して下さった。
それだけで、感激なのに、
なんと、この『つか版・忠臣蔵』をもっと多くの人に知って欲しいから、と。
今まで誰に勧められてもやらなかった、というご自身のブログを昨日、スタートされた。
『つか版・忠臣蔵』を観て、その勢いで、翌日に。
あの運命の時、その場ですぐ、編集者たちに電話をかけて下さったのと同じように。
なんか、嘘みたいな話だけど、実話です。
ここを見て。
http://ameblo.jp/torukenjo/
アメブロ で。
『ケンケンかく想いき』というページ。
幻冬舎社長、見城徹さんの日記です。
そこに『つか版・忠臣蔵』のことを書いて下さっています。
胸がぐっと熱くなります。
泣くしかないでしょ。
私こそ、生きていてヨカッタと思いました。
その後、ちょっと疎遠になっていたのです、というよりも、角川を離れられ、幻冬舎を始められてからは、
すっかり時代の寵児であられ、日本を代表する文化人であられ、ビジネスのリーダーであられ……
我々のちっぽけな公演のご案内など軽々にするのも、憚られる気配になっていた。
ただ、
この『つか版・忠臣蔵』は観て頂きたかったので、心の底から感激です。
それにしても、ホントに……
我々の節目節目に、つかさんがいてくれます。
なんか人間のチカラを超えた、不思議なチカラを感じずにいられません。
いやいや、これこそ正真正銘、人間のチカラというものなんでしょう。
人間っていいなあ、と叫びます。