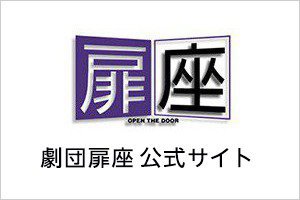東京の喜劇
六角に、三木のり平 みたいなことやってもらおうと思ったのである。
若い人は、知らぬであろう。
そういう役者がいたのである。
東京の喜劇人である。
映画やテレビで大活躍した。
桃屋の、メガネのオジサンといえば良いか。
マスコミ的にも人気者であったが、本分は舞台にあり、
喜劇で有名だったが、
性根は、シリアスで、
前衛も古典もこなす、すごい演劇人だった。
晩年は俳優座で、演出したり、別役実作品に出たりしていた。
私は自称最後の弟子で、いろんなことを教わった。
この人が、作った舞台は
たとえばまだ古い明治座で、やったお笑い四谷怪談みたいなものでは
当時社会的な話題だった、宇宙ロケットのドッキングと、一方歌舞伎界で、大人気だった、市川猿之助 の宙乗りをパロって
ラストシーン、死んだ お岩とイエモンが、あの世で、ドッキングするという、
それを宙乗りでやるという、
ドタバタ、あちゃらか をやっていた。
という。
私しゃ、その頃、そんなもの見ちゃいないから、後で聞いた話だけど。
でも、
今の吉本新喜劇みたいなのとは違うんである。
役者それぞれのギャグで笑かすんじゃなくて、
筋のあるホンがあって、演出があって、役者は役を演じつつ、その中で突飛な展開や趣向を凝らして笑わせる。
浅草の軽演劇から連綿と続いてきた、東京の喜劇の伝統につらなる舞台である。
中心は、あくまでも演技にあり、
ふざけたことをやっても、それがイチイチ、歌舞伎とか、落語とか、伝統的な美意識や、粋の精神を秘めている。
大阪の、コテコテとは違う、
ちょっとスカした、インテリ趣味というか、
まあ、粋ってヤツだな。
実際、全盛期の浅草あたりで、喜劇やってたなかには、すごいインテリが多かったというし。
大正時代のドタバタの手本も、バリにあったり、ジャズにあったり、してたんだよな。
でも
そういう世界の巨匠・菊田一夫がいなくなり、のり平が去り、モリシゲが去り、
東京の喜劇は、めっきり衰退してしまった。
井上ひさしさんも、それを憂いていたものよ。
あの方は、芝居の基本は喜劇にあり、といつもいってた。
『オリビアの聴きながら』に出て貰った石井けん一さんも、のり平さんの追っかけだったことがあり
8月辺りは、そういうことをよく語り合っていた。
で
いつか、東京の喜劇みたいなの、しっかりやろうね、と。
実は、六角は、のり平さんに可愛がられていた。
のり平さんが監修してくれた舞台に何度か出ているのである。
メガネしゅうまい
と、のり平さんは六角を密かに呼んでいた。
しゅうまいは元気かい、と、よく気に掛けてくれていた。
世の中に対するスネ方とか、
きっと、ご自分に近いモノを感じていたのだと思う。
のり平さんという人も、
可笑しいけど、怖くて、死ぬほど馬鹿馬鹿しいことするけど、限りなく明晰な人だった。
ダメ出しは辛辣を極め、よく役者たちは泣かされていた。
人の悪口言わせたら、惚れ惚れとする歯切れの良さと、意地悪さだったものよ。
江戸っ子ってこういうのなんだろうなと、私もよく叱られつつ、この語調を覚えたいと思った。
のり平さんとよくお会いしている頃、思えば私たちはまだ若かったのだ。
芝居についても、まだよく分かってなかったなと思う。
今、会えば、ずいぶん身に付くものもあっただろうに。
我々も年取ってきて、この先、何を目指すのか、改めていろいろ思うんだけど
のり平さんがやってたこと、やろうとしてたこと、は見様見真似でも継承したいなと思うのである。
もちろんそのままじゃ今の時代にフィットしないだろうから、創意工夫しつつだけど
その時に、六角精児が新時代の、三木のり平、にならんかなあと、思っている。
そんな『端敵☆天下茶屋』今日は、夜の公演です。
いよいよ、千秋楽が近づいて参りました。
ご来場はお早めに。
とにかく
三木のり平 はもう一度、見直されて良い人です。