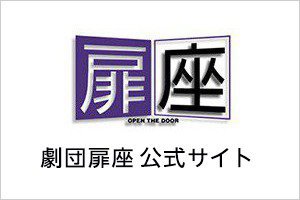仕上げ と 取りかかり
『フレンド 今夜此処での一と殷盛り』もそろそろ稽古の大詰め。
すでに通し稽古も、数回行い、今はブラッシュアップの時期。
ただ衣裳、小道具なんかが本番用に順次、替わって来て、臨場感増しとともに、想定外的なこともみつかり、それを調整して、更に変更してゆくといった感じ。
今回、実在の文学青年たちの話を戯曲に書くにあたって、
わしが、留意したのは、文学に詳しくなくても、現代史を知らなくても、ちゃんと話が分かって、かつ面白いこと。
というか、インテリだけの世界観にしないこと、であった。
わしは決してインテリではないが、それでもまあ、文学青年のなれの果て、みたいなところはあるから、小林秀雄だの、大岡昇平だの、そんな名が出てくると、つい知識を詰め込みたくなるんだけど、そこをこらえて、
登場人物たち皆を、安酒場の住人として、描くことに腐心した。
いわゆるひとつのアングル、というか視点みたいなものを、徹底的に庶民に求めることにしたのである。
その代表が、佐津川愛美さん演じる、酒場の娘・秋子である。
この役は創作。
『中原中也の手紙』に紹介された手紙に、
中也が、安原氏に、どっかの酒場のウェイトレスの女の子と、お前、付き合えよ、みたいにやたら奨める手紙があるんだが、それをヒントにして、創作した役。
でこの役が、今回のわしの、庶民の視点から、文学青年たちを描くという試みの第一のキーパーソンになる。
この役が上手く生きるか否かで、出来が大きく変わると言っても過言ではない。この役の周囲に、さらに文学とは一見無縁の庶民たちがいて、彼女がそれをつないでゆく。
そして今回、はじめてお会いした、佐津川さんが、この役を見事に演じてくれている。
まだ幕が開いてもいないのに、そんなに誉めちゃダメなんだけど、ふたりの男の友情の話に挟まれつつ、しっかり生活者として生きて、しかも魅力的にアクションして、彼らの存在を、我ら非知識人や、現代にまでつないでくれている。
こないだ通し見に来たどこかのマネージャーさんが、自分のとこの俳優のことはそっちのけで
佐津川さん、仕上がってますねえ、と興奮していた。
実際、とてもよろしい。
わしがしたのではないが、キャスティング偉い。よくぞこの娘を連れてきてくれた。
ま、佐津川に限らず、とにかく今回は、キャスティングが良いと、稽古が始まってすぐに感じ、
稽古が進むにつれて、それが深まり、
そしていよいよ、仕上げの時期に来て、通しを見るたび、
これはもう、奇跡的にバランスとか、配置とかがキマった舞台になると確信している。
出演者たちも皆、そう感じているのだと思う。
始まる前から、終わって別れる時のことを思って、哀しくなるような、仲の良さである。
もちろん、開幕して、キチンと拍手を頂かなきゃ、そんな気分もすぐに霧散してしまうから、ここからしっかりラストスパートする。
一方扉座『NAOTORA』も、台本が出演者に渡されて、いよいよ始動。
こっちは戦国時代の話。
幕末に安政の大獄で暗殺された、大老・井伊直弼のご先祖様。
幕府を開いた頃の徳川家康の懐刀だった井伊直政の、叔母にあたる、井伊直虎の物語。
女だてらに、直虎という名を名乗り、城主となった、井伊家のひとり娘である。
彼女が男の武将たち以上に頑張って、家を繋いで、直政を育てて、潰れかけていた井伊家が、後に三百年続く名家となったのであった。
しかしこちらも
歴史通でなくても、楽しめるように創ることに留意する。
たぶん私はインテリが嫌いなんだね。
自分が中途半端にインテリなのも、かなりイヤである。
将来は、立派な無学の男になりたい。
そもそも、主な出来事は、歴史にならうけど、人間たちの言動などはほぼわたしの創作である。
三代目・猿之助の元で研鑽した、スーパー歌舞伎の台本書き手法を駆使して、
歴史の名を借りた、骨太い人間ドラマを、描くつもり。
ただしセリフは多い。
ぐわーーーーーーっと、セリフをしゃべる。
そこはもう、シェイクスピアのように。
セリフが言えない座員はクビにしていく所存。
それぐらいハードにやるので、乞うご期待。