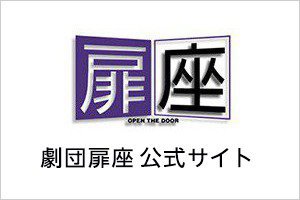シェイクスピア
今年も明治大学で、シェイクスピア・プロジェクトの公演があり
監修という名の、お手伝いをしているワケだが
今回の『なおとら』は、この3年、学生たちのシェイクスピアを見守り続けたことが、キッカケになって取り組んだものだ。
シェイクスピアという作家に改めて興味を持った。
いったい何をどう書こうとしたのか。芝居で何をしようとしたのか。
歴史劇であれ、喜劇であれ、悲劇であれ
根底に流れるモノには、創作の肝というかね、同じような要素がありそうな作家である。やっぱシェイクスピアだなあ、と思わせる何か。
よく書けた芝居ということに加えて、そういう何かが人の心に刺さるから、これだけ上演されているに違いなのだ。
なにしろ400年ずっと、消えずに人気作家であり続けている人だ。
もちろん及ばずながら、不遜ながら、なんだけど。
劇作生活、37年にして、このエベレストみたいな高き峰を仰ぎ見る、境地に至ったのだ……
というのはちと大げさだが。
も一回、エンゲキの原点みたいなものに取り組もうと思ったことは嘘じゃない。
それは、みんなが知ってるエンゲキである。400年ぐらい、みんなが楽しんできた、笑ってきた、泣いてきた、エンゲキである。
時代によってドラマは変わると言うけれど、ホントに、そんなに変わるのかね。
だったら、シェイクスピアなんか、とっくに消えてなきゃおかしいじゃないか。
と、この歳になってしみじみ思うのである。
そして歳を重ねてこそ、わかる味わいがシェイクスピアにはたくさんある。
若い頃に触れて、なんだコレ、ダサイ、古いと感じたことが、実はこんなにしみじみ心に迫ってくるモノだったのかと気付かされること。
マクベスのバーナムの森とかさ。
森が動かない限り、マクベスは負けないと言われるんだけど、案の定、森は動く。
でもそのトリックが限りなくチープで、だいたい上演でのガッカリポイントなんだけど
歳をとるとわかるんだ、若者諸君。
森が動いて迫って来る恐怖が。どんなにチープでも、動く森の恐ろしさ。 そういうことが人生にはあるってこと。
まあ、これからの残り作家生活に、またひとつ取り組むべき課題、楽しみなテーマを得た、というところだ。
ところで、小田島クンが昨日来てくれた。かのシェイクスピアの翻訳家の小田島雄志先生のご子息で、シェイクスピアは翻訳しない、早稲田大学の偉い先生で翻訳家の小田島恒志さん。
私とは、数少ない大学時代からのエンゲキ的友人だ。
忙しいのに来たんだから、つまんなかったら怒るよ、と始まり前に言ってきた。
今回はシェイクスピアのように書いたから、と言うと。
そんなに、つまんないのか と。
なかなか気の利いたことを言う。
さすが小田島2代目と褒めておく。
で、終わった時にひと言。
シェイクスピアより面白かったよ。
実は36本もあるんだからね、シェイクスピア。きっちり駄作と切り捨てられてるモノもなかにはあるし。
お互いザックリすぎるだろー。
そんなナオトラ 今日はお昼だけの公演です。